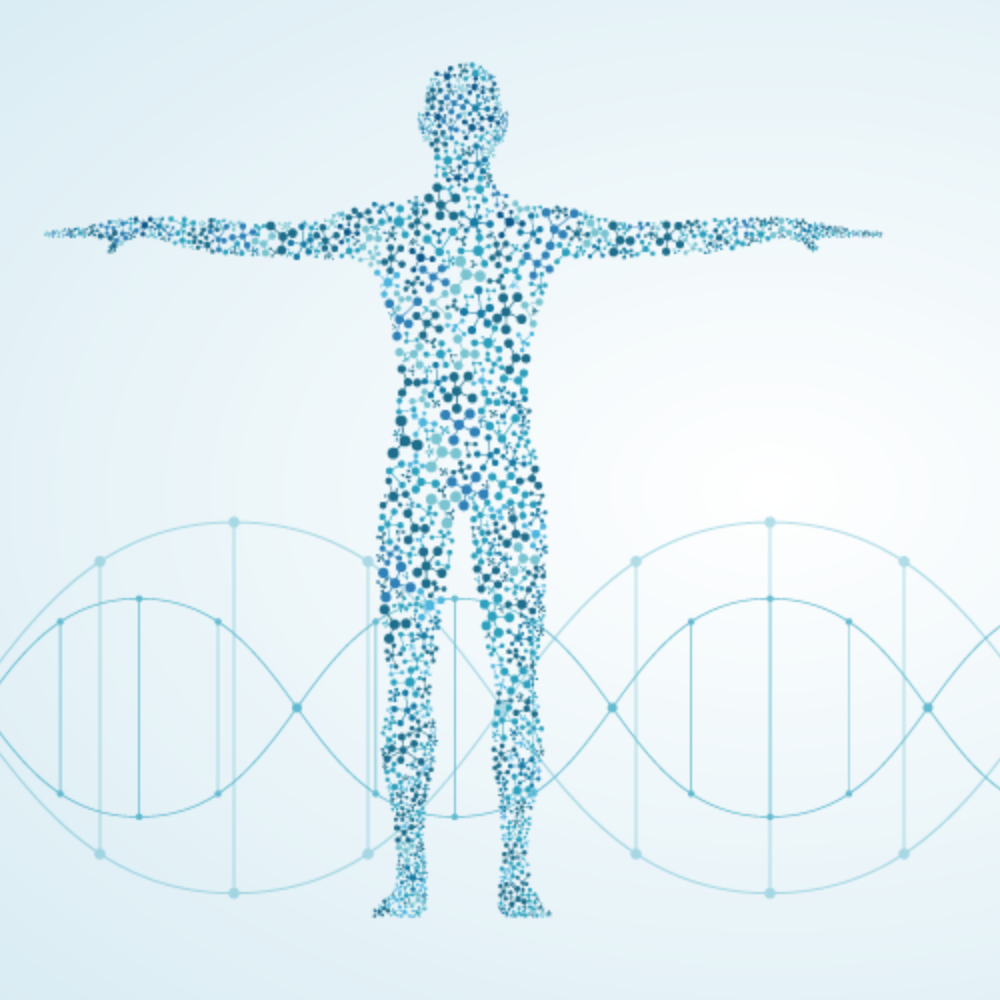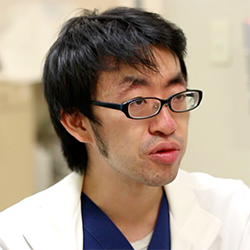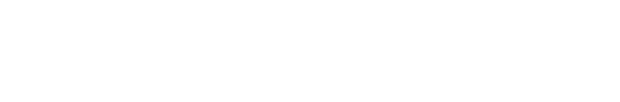2024/03/23
東邦大学教育賞を受賞致しました。
大学病院は「高度先進医療を行う専門医の集団」であると同時に、「多くの学生さんや研修医などの初学者が初めて患者さんと触れ合う教育病院」でもあります。この視点に立ち、「専門医療機関と教育病院としての責務の両立が大学総合診療科の使命」と考えて2014年に母校に戻り、「卒前教育に直接関われることが大学病院の最大の特徴」と考えて、私なりに教育に力を注いでまいりました。
しかし、大学病院という多様な価値観を持った医療者・学生の教育は、私自身の未熟さもあって、思った以上に難しく、思うようにできないままに十年が過ぎてしまいました。日々の業務に押し流されて、かつての教育への情熱をなくしまったというのが正直なほろ苦い思いです。
そのような状況でしたが、3月22日に令和5年度東邦大学教育賞を受賞致しました。
「どうして私が?」と思いましたが、学生さんが私の講義を高く評価してくれたことが受賞の機会に繋がったようです。
私の講義を聞いて海外への挑戦に興味を持ってくれた学生もいたようで、私が学生時代に講義を聞いて、自分の将来に夢を描き、心躍らせたのと同様に、私の講義が学生さんの挑戦を後押しできたと考えると、感慨深いものがあります。
私を指導して下さり、薫陶を受けた数多くの先生方が与えてくれたものを少しでも後進に伝えることが恩返しであり、私自身も学び続けていかなければならないという自戒の念を新たにしました。
この賞を励みに、今一度、教育者としての自分を省みて、再び教育と向き合いたいと考えております。
ご推薦いただいた盛田医学部長、ご指導いただいた先生方、そして学生さんに感謝申し上げます。
文責:佐々木 陽典
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しく見る
2024/03/18
本多満教授退任記念祝賀会が開催されました。
去る3月10日に当科本多満教授の退任記念祝賀会が開催されました。会場となったオークラ東京の会場には200人以上の参加者が出席され、本多先生の「卒業」をお祝いされました。本多先生のざっくばらんで、気さくなお人柄が伝わってくる温かくて楽しい退任祝賀会でした。
本多先生は長年にわたって、当講座救急科のリーダーとして、当医療センターの誇る救命救急センターのセンター長として私達のご指導にあたってこられました。私自身は研修医時代から救命センターでの急変対応やクモ膜下出血の緊急手術等、本多先生から直接ご指導いただき、医師としての根本を教えていただき、思い出は尽きません。本多先生は脳外科・救急医として大学の内外でご活躍されただけでなく、医師・看護師の教育にも大変熱心で、東邦大森ICLSを開催回数120回以上を誇る老舗ICLSコースに育て上げました。かつての私自身を含め、多くの研修医がこのコースでICLSを学ぶ機会をいただき、東邦大学3病院のみならず、多くの病院の看護師・医師・救命士が高度な心肺蘇生を学んできました。私が現在ICLSディレクター、JMECCインストラクターとして救急医学会や内科学会で心肺蘇生の教育に携わることができているのも、全て本多先生にご指導いただけたからです。医師・看護師・救命士を分け隔てなく育ててくださる本多先生のお人柄のおかげで今の大森病院の救命センターの明るい雰囲気があるのだろうと感じています。
退任祝賀会では、研修医の頃にご指導いただいた救命センターの指導医の先生方や仲の良かった同級生と久しぶりに再開することができ、大規模な同窓会に参加しているような気分でした。研修医時代に当直中に夜を徹してご指導いただき、外来も見学させていただき、「お前は夏休みも取らずに研修ばかりで可哀想だから」と鹿児島の心臓病学会にまで連れて行ってくださり、私のロールモデルのお一人である笹尾先生とは研修医の時以来、16年ぶりにお会いすることができました。同級生からは「お前のこと、すっかり忘れていたぞ」と言われていましたが、私のことを覚えてくださっており、感激しました。救急外来で対応したクモ膜下出血患者の初期対応・血管造影・髄腔ドレナージ・緊急手術まで、つきっきりでご指導くださった坂田先生との再会も16年ぶりでした。本多先生は4月以降も特任教授として引き続き東邦大学でご尽力いただけるとのことで、心強い限りです。教授退任という大きな節目を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。本祝賀会の発起人である瓜田先生、藤井先生(心臓血管外科)、鈴木先生に心より御礼申し上げます。
結びのご挨拶をされる本多先生です。
会場は多くの参加者で賑わっていました。
素晴らしい会場でした.
文責:佐々木 陽典
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しく見る
2024/03/12
繁田先生が日本プライマリ・ケア連合学会関東ブロック支部会で症例提示してくれました!
3/10(日)に当科の繁田先生が日本プライマリ・ケア連合学会関東ブロック支部会でTokyo GIM conference出張編として、大変興味深い教育的な腹痛の症例を提示してくれました。
Tokyo GIM conferenceは関東(最近は全国から!)の新進気鋭の医師が集まって教育的な症例について議論するハイレベルな症例検討会です(私も世話人・コメンテーターを務めております)。
今後、しっかりと症例報告として発信したいと思いますので症例の詳細は省きますが、診断のエキスパートであるコメンテーターからの鋭く詳細な質問に対しても澱みなく答える繁田先生の様子から、繁田先生が患者さんの生活状況が克明に描けるような病歴聴取を行い、診断を諦めない姿勢を持って患者に接していることが実感されました。繁田先生の詳細は情報提示とコメンテーターの鋭い質問によって議論は発熱し、参加された皆さんにとって学びのあるカンファレンスができたのではないかと思います。繁田先生の臨床医としての資質に感銘を受けました。
繁田先生、お疲れ様でした!
司会の宮上先生、コメンテーターの先生方、参加者の皆様、ありがとうございました。
カンファレンスでフロアの参加者から共有していただいた語呂:
CTで診断できない腹痛 “PM BAD LUNCH” 出典: Saint Frances Guide to Impatient Medicine
Porphyria
FMF
Black widow spider bite
Angioedema、adrenal insufficiency
DKA
Lead toxicity
Uremia
Neurological diseases, Narrow angle glaucoma
Ca↑
Herpes, Hereditary angioedema
文責:佐々木 陽典
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しく見る
2024/03/09
医療リアルワールドデータ活用人材育成事業を修了致しました。
当院の診療データを手作業で解析して行う研究の限界を感じ、仕事を続けながら、臨床研究者としてのスキルアップを図る方法はないかと思いあぐねていた2021年にたまたまポスターを見かけ、「これだ!」と思って出願し、入学が叶ったのが「東京大学医療リアルワールドデータ活用人材育成事業」でした。
このプログラムは、電子カルテシステムの普及やデータ収集基盤の社会的整備に伴って創出される大規模な医療リアルワールドデータについて、具体的な医療課題解決と知見創生に必要なデータ処理技術を習得し、それを自ら実践でき指導者層にもなりうる人材育成を目的として、実践的技術と知識を修得する教育プログラム・コース(2年間で162時間履修)です。講義は土曜日と平日の夕方に東大キャンパスとZoomを併用して行われました。
東京大学医学部を訪れたのはほとんど初めてで、そのキャンパスの広さ、美しさに驚き、通学できること自体が喜びでした。キャンパスの並木はどれも非常に太く、歴史を感じさせました。ドイツ人医師の銅像が数多く点在しており、東京大学医学部から全国に広がっていった日本の医学教育がドイツ医学に根ざす部分が多いことが実感できました。
とても出来のいい受講生とは言えず、無事に修了できる自信がなかったのですが、無事に修了が認められ、3月2日(土)に修了式に出席致しました。
あっという間に40歳半ばになり、腹は出る一方で、医局では講師という中堅の立場になり、他の業務と並行しながらの勉強は大変でしたが、教育熱心な先生方に懇切丁寧に教えていただき、実際に自分で手を動かして試行錯誤しながらデータを取り扱う経験ができました。そして、医師以外にも看護師、病院のデータ管理部門の第一線で働いているスタッフ、大手製薬会社の統計専門家まで、多種多様で意欲に満ち溢れた同級生の熱意に支えられて、なんとか2年間を乗り切ることができました。自分自身の努力不足で十分に結果を出せず、悔しい部分もありますが、一方で、自分の体力と能力を考えると、これ以上頑張れなかったような気もしており、履修できたことをとても嬉しく思っています。そして素晴らしい受講生の皆さんと繋がりができたことも大きな財産だと感じております。
自分自身で独立していわゆるビッグデータ研究を実践・指導するためにはまだまだ課題が山積していますが、これをスタートに引き続き頑張ってゆきたいと思います。
私と同じように臨床で頑張りつつ、ビッグデータやAIを用いた研究について勉強したいという方はぜひサイトをご覧ください。
https://www.med-rwd.jp
修了式での受講生の集合写真:素晴らしい仲間に恵まれました!
修了証! 2年間の努力の証です。
講義を受けていた研究棟です。
隣は東大病院でした。東大キャンパスは歴史を感じさせる素敵な環境でした。
文責:佐々木 陽典
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しく見る
2024/02/07
大学病院総合診療科と健診受診者の慢性腎臓病の有病率の比較に関する論文が掲載されました。
日本の総合診療科は過度の専門分化への反省に基づいて、独特の発展を遂げてきた新しい領域であり、どのような患者を診療しているのか等も十分に知られていません。慢性腎臓病は血液透析だけでなく脳卒中や心筋梗塞等の原因でもある生活習慣病です。
そこで、当科で診療している患者さんと城南地区で健康診断(特定健診)を受けた方々で、どのような違いがあるのかについて、厚生労働省が提供しているデータを活用して研究した論文がJournal of Hospital General Medicineに掲載されました(http://hgm-japan.com/english/jhgm2024-6-1/ )。
本研究の結果、当科を受診している患者さんにおける慢性腎臓病の有病率(15.2%)は城南地区健診受診者は有病率(10.6%)の1.4倍であり、腎臓専門医が診している患者さんでの有病率(20.6%)と地域住民集団における有病率(4.2-16.2%)の中間に位置することが明らかになりました。
この結果から、大学病院総合診療科における慢性腎臓病の有病率は城南地区健診受診者の1.4倍であり、腎臓専門医が関与する前の患者集団を反映している可能性が考えられました。
今後も総合診療科がどのように日本の医療に貢献しているかを客観的に示す研究を継続してゆきたいと考えております。執筆に際してご指導・ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
近日中にJ-STAGEで全文が閲覧可能になる予定です。
上に示すように大学病院総合診療科(UGHMD,左)を受診する患者さんは健診受診患者さんよりも高齢者が多いことも示されました。
文責:佐々木 陽典
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しく見る