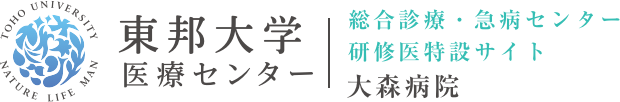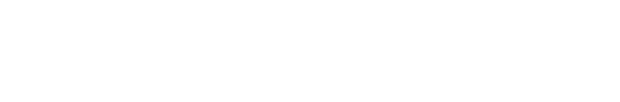5月19日に京都で開催された日本プライマリ・ケア連合学会でJUGLERの一員としてセッションに登壇致しました。
JUGLERとは、佐賀大学多胡先生の呼びかけのもと、昨今の大学病院総合診療科の現状に危機感を抱き、解決策を見出すべく昨年10月から活動を継続しているJapan University General Medicine Leadership and Education Roundtable(獨協大学志水先生発案)の略称です。
現在は、佐賀大学多胡先生、獨協医科大学志水先生、千葉大学鋪野先生、順天堂大学高橋先生、島根大学和足先生、私の6名がコア・メンバーですが、どんどん仲間の輪が広がっています。
既存の学会や専門医制度の枠にとらわれず、若手のリーダーたちで自由に議論して自分たちの「理想の病院総合医」の姿を明確にして大学病院総合診療科の必要性を発信してゆくことを使命としており、5月19日に京都で開催された日本プライマリ・ケア連合学会では、若手医師にもイメージしやすい「理想の病院総合医」を共有すべく「病院総合医のコア・モジュール」について提言・議論を行いました。
予想を遥かに上回る数の先生方にご参加頂き、インタラクティブな進行方法で実りあるディスカッションを行うことができました。また、多くの先生方から励ましのコメントをいただき、「大学病院に総合診療部門は必須である」との確信を強めました。
引き続き、若手の先生方にあるべき病院総合診療医像を明示し、全国の大学で環境や背景の違いを共有し、その垣根を越え、病院総合医ひいてはこの領域の未来のリーダーを育成すべく、活動を続けて参りたいと思います。
ご参加、ご協力、ご指導いただいた各方面の先生方、誠にありがとうございました。

私だけお腹がすごく出ていて笑ってしまいましたが、(私以外は)カッコよくて素敵な写真です!

Mentimeterを利用した会場からのご意見・ご質問に見入っているメンバー達

セッション後の記念撮影です。
文責:佐々木 陽典
———————————————————————————————————–

5月10日(金)にTokyo GIM conference79で症例提示させていただきました。
先日告知させていただいたとおり、5月10日(金)19:30から川崎幸病院で開催されたTokyo GIM conference 79で、外来で経験した印象的な症例を通じて、患者さんの受領行動・解釈モデル、患者さん自身が言語化できていない隠された主訴、医師の抱く違和感の重要性、腹囲増大の鑑別診断等についてお話させていただきました!
発表を聞いていたレジデントから「昨日、全く同じような症例を経験したので、とても参考になった!」と言ってもらえ、医者/発表者冥利に尽きるなと感激しました。
夜遅くからの開催にもかかわらず教授が来てくださり、写真まで撮ってくださいました!
もう一例の発表症例と私の症例が同じ疾患/病態を扱ったもので、偶然に驚きながらもとても勉強させていただきました。
ご開催いただいた原田先生はじめ世話人の先生方、根本先生、紀平さんはじめ川崎幸病院の皆様、そしてご参加いただいた皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

文責:佐々木
———————————————————————————————————–

柏木先生が執筆したClostridium perfringensによる肝膿瘍に関する英文症例報告が掲載されました!
総合診療・急病センター感染症科レジデントの柏木克仁先生の執筆した初の英文症例報告が日本病院総合診療医学会雑誌15巻2号に掲載されました!
柏木先生は東邦大学医学部を卒業後、同医療センター大森病院で卒後臨床研修を修了しました。各診療科の医師が特定分野の診療のみを行い、患者さんが長時間待たされ、院内を巡礼している都心部の大学病院の現状に疑問を持ち、感染症を中心として幅広い疾患の診療ができる「昔ながらのお医者さん」を目指して2017年に総合診療・急病センター感染症科に入局してくれました。
豊富な知識、冷静な判断力を持つ一方、患者さんにかける情熱に溢れており、文字通り” Cool head and hot heart”を持った臨床医であり、その仕事ぶりは周囲から高く評価されています。
数時間で死に至ってしまう激烈な経過を辿るClostridium perfringens(ウェルシュ菌)による肝膿瘍について、先行文献をつぶさに調べ上げ、国際医療センターでの武者修行という過酷な環境の中でじっくりと書き上げてくれた貴重な症例報告です。
柏木先生、本当にお疲れ様でした!

文責:佐々木
————————————————————————————

5月10日(金)19:30から川崎幸病院で開催予定のTokyo GIM conference79で症例提示させていただきます。
前回Tokyo GIM conference 78 Clinical Picture Festivalに引き続いて5月10日(金)19:30から川崎幸病院で開催予定のTokyo GIM conference 79で外来で印象に残った症例を提示させていただきます。川崎駅徒歩圏内ですのでお時間のある方はぜひご参加ください。

文責:佐々木
——————————————————————————————-

東京駅丸の内改札口に「総合医」の大きなビジョン!
東京駅丸の内改札口に「総合医」の大きなビジョン!
2年前に東北医科薬科大学の入学式で、学長の高柳元明先生が「君たち100人は、全員総合診療医になってもらいます!」と訓示を述べているのを聞いて、感激のあまり身震いしたことを、昨日のことのように覚えています。
先日、東京駅丸の内中央改札口を出たときに飛び込んできたのが、「総合医」の文字でした。

自治医科大学のPVでした。思わず、パチリ!

体系を基礎から確実に積み上げる方法は、数学と共通する医学教育の古典的な考え方でした。しかし、多様化する学問体系を限られた時間で学修することは極めて困難です。一分野で大きく階段を登り体系を見渡すと、それまで違う領域に見えていた分野が、意外なほどの同じシステムで生命活動を営んでいることに気づきます。自分の専門領域のスキルが、他の領域でも十分に臨床推論を展開できることを発見できる場合があります。しかしながら、階段を上っても体系を見渡すマインドを持てない指導医は、極めて多い各分野の共通点を見逃してしまい、アルゴリズム、ガイドラインに頼る診療となってしまいます。
本学は私学であり、多くの卒業生が地域医療に戻っていきます。多くの診療科を有する大学病院ですが、見渡す謙虚さを持って診療、研究、教育を展開して生きたいと考えています。
「大学だから・・・」というフレーズは、診療の場で患者さんに投げかけるものではありません。自分の診療スキル、思考回路、学術的探究心にこそ「大学だから・・」と問いかけて研鑽していかなくてはなりません。
自治医科大学、東北医科薬科大学に続く、総合診療マインドの溢れる大学にしたいと、心から願っています。
文責 瓜田純久
———————————————————————————————————–